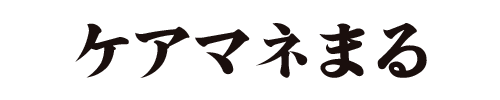こんにちは、ケアマネジャーのまるです。
今回は、生活保護の中でもあまり知られていない、「移送費」について解説します。
「そんなのもあるの?」と思った方、意外と多いんです。実はうまく活用すれば、生活を支える大きな助けになりますよ。
■ 移送費とは?
移送費とは、生活保護を受けている方が「やむを得ず移動しなければならない」場合に支給される費用のことです。
対象になるのは、例えばこんな場面です
- 遠方の病院への通院や入院→ほぼこれ!
- 高齢者施設や福祉施設への入所・転所
- 身寄りがなく、別の自治体へ移動しなければならない場合
つまり、自力での移動が難しく、放っておくと生活や健康に支障が出るようなケースが対象なんです。
■ どんな交通手段が対象になるの?
基本的には、もっとも安く合理的な手段が選ばれます。
バスや電車が一般的ですが、どうしても移動が困難な方にはタクシー代が認められることもあります。
ただし、それにはしっかりとした理由が必要です。
■ 誰がどうやって申請するの?
移送費の支給は、原則としてケースワーカーの判断に基づきます。
本人や支援者が「移送費を出してもらえませんか?」と申し出た上で、ケースワーカーが必要性を確認し、支給を判断します。
ここで注意したいのが、必ず事前に相談すること!
勝手に移動してしまったあとでは、支給対象外になることもあるんです。
私の経験では、継続的な通院が必要になってからケースワーカーに移送費の相談をしても遡って移送費が支給されるパターンが多いです。
■ケアマネが移送費を役所のケースワーカーにお願いする流れ
私がいつもやっている移送費についての流れをお伝えします。私の担当の利用者はタクシーしか利用していないので、タクシー利用に限られますが参考にしてください。介護タクシーも対象になっています。
市区町村で違いはあるかもしれませんがおおよそ下記のような感じではないでしょうか。
本人や家族が手続きをできるようであればお願いしましょう。
①利用者が継続的に通院が必要になる(一回の通院で解決するようであれば移送費は出ないでしょう)。
②生活保護担当のケースワーカーにその病院までの移送費をお願いしたいと伝える。ケースワーカーから「(通院は)いつからですか?」と聞かれる。
③内容が認められたらケースワーカーから給付要否意見書を預かる。
④給付要否意見書を通院中の病院に持参し「通院は必要(月に1回とか月に2回など)である」と記載してもらう。私がもらうときはほぼ半年の期間。なので半年に一度は病院に給付要否意見書を持っていき(利用者が受診するときでも良い)記載してもらっています。
⑤次は給付要否意見書を移送の会社(タクシー会社)に持参し記載してもらう。
⑥それを生活保護担当のケースワーカーに提出する。タクシー会社が市役所に提出してくれる場合もあります。
※“ケアマネの業務”ではありませんので基本は本人や家族に役所のケースワーカーに連絡してもらいます。
■料金の支払いについて
これは大きく分けて2パターンあります。
①利用者が通院した時に支払って、そのレシートを生活保護のケースワーカーまで持参して、次の保護費が支給されるときに移送費も振り込まれる。
②利用者が通院した時に支払わず、タクシー会社が直接請求書を役所に提出し、役所から直接タクシー会社に振り込まれる
個人的には②の方が楽ですね。
■ 施設見学や通院付き添いでも出る?
基本的に、任意の見学や付き添いなどは対象外です。
ただし、どうしても本人だけでは行けない状況などがあれば、ケースバイケースで認められることもあります。
迷ったら、とにかく役所の担当の方に相談です!
↓シャドーワークについて弁護士が法的根拠をもとに明確に記載してあるのでモヤモヤがすっきりします!
■ まとめ
今回の内容は自治体で対応が違ったりするので、参考程度にしてみてください。
生活保護の移送費は、うまく活用すれば大きな負担を軽くすることができます。
でも、そのためには「事前の相談」と「必要性の説明」が大切。
もしご自身や周りの方が該当しそうな状況であれば、まずは役所のケースワーカーに声をかけてみてくださいね。
📌この内容をショート動画でも解説しています:新人ケアマネ応援チャンネル
👉 知らない人が多い!生活保護の移送費についてざっくりまとめてみました